登記の専門家です。
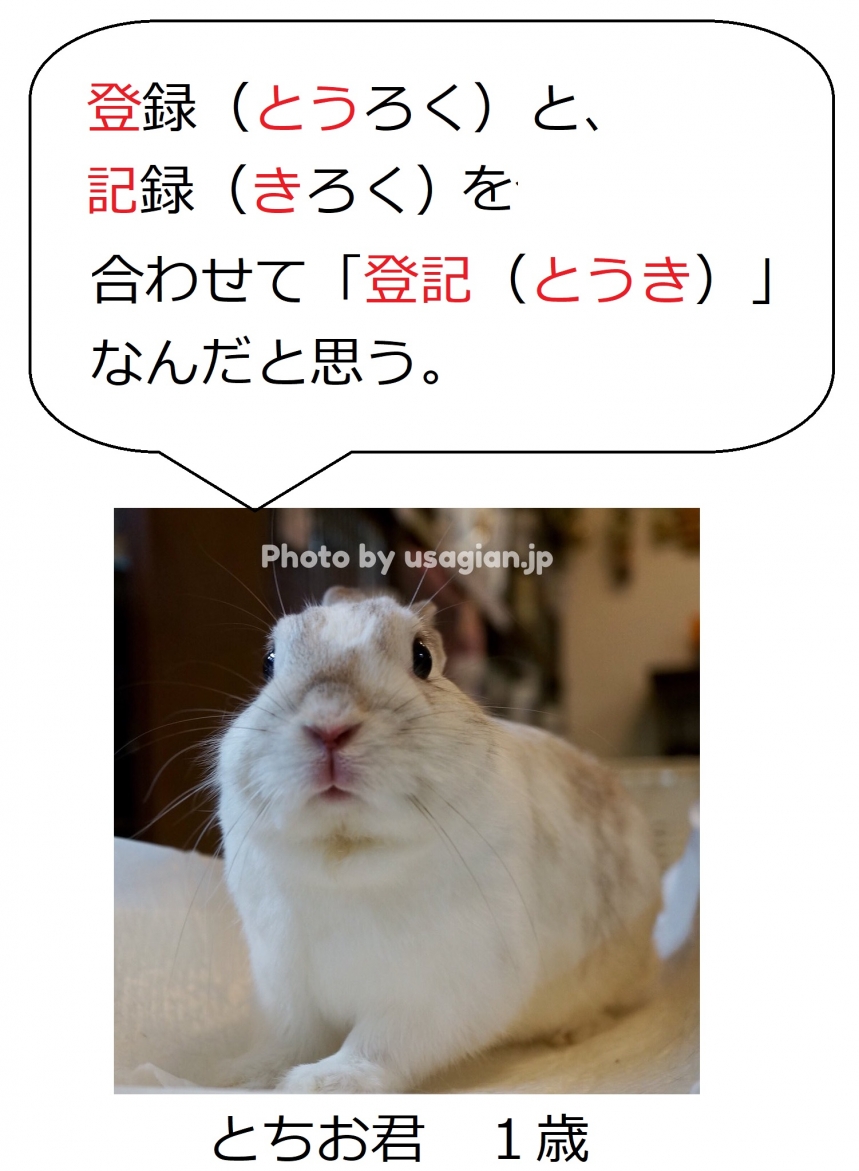 この土地・建物は、だれのもの?この会社は、どんなお仕事をしているの?ということを、国の役所である「法務局(ほうむきょく)」に登記する(=届け出る)仕事です。登記により、持ち主の住所・氏名や、会社の内容が、法務局が発行する、証明書に書かれます。みなさんは、この証明書を見ることにより、「この土地は、●●さんのもので、間違いない。」「この会社は、きちんと営業しているんだ」ということを、知ることができます。証明書は、誰でも見ることができます。そうでないと、
この土地・建物は、だれのもの?この会社は、どんなお仕事をしているの?ということを、国の役所である「法務局(ほうむきょく)」に登記する(=届け出る)仕事です。登記により、持ち主の住所・氏名や、会社の内容が、法務局が発行する、証明書に書かれます。みなさんは、この証明書を見ることにより、「この土地は、●●さんのもので、間違いない。」「この会社は、きちんと営業しているんだ」ということを、知ることができます。証明書は、誰でも見ることができます。そうでないと、
「●●さんから買った土地は、本当は▲▲さんのものだった! お金を返して!」
「●●会社なんて、本当はなかった! この商品は、不良品なのに!」
というトラブルだらけになって、
世の中「北斗の拳」になりますからね。
YOU ARE SHOCK!
どんな質問・相談ができる?
 司法書士は、民法「みんぽう」という法律を勉強していますので、
司法書士は、民法「みんぽう」という法律を勉強していますので、
「物の持ち主について」
「お金の貸し借りについて」
「離婚について」
「人が亡くなったときについて」
などの相談を、お聞きします。
最近、増えているのは、 成年後見 についての相談でしょうか。これも、家族について決めた、民法の一部です。
そして、
「不動産を売った、買った、もらった。」
「親が亡くなったので、子供が財産を引き継いだ。」
「会社の住所や、役員が変わった。」
このような相談は、登記が必要なことが、ほとんどで、
登記の相談は、司法書士しかできません。
(または、法務局に直接、相談するか)
成年後見の仕事って、なに?
 20歳未満の子供には、親が子供の代理をすることができると、法律で決まっています。
20歳未満の子供には、親が子供の代理をすることができると、法律で決まっています。
そして、子供が20歳以上になると、法律では、子供ではなくなり、親でも代理はできません。
(20歳以上でも、親が代理できたら、「親が反対したら、子供は何もできない。」という状態が、親が生きている間、ずっと続くことになるからです。)
しかし、20歳以上でも、障がいがあったり、高齢による物忘れなどにより、自分の思ったことを、うまく相手に伝えられない人もいます。
このような人たちのために、大人の代理を、別の大人がすることができる、「成年後見制度(せいねんこうけんせいど」という決まりがあります。
家庭裁判所に申し込みをして、認められた人が、代理人となることができます。
成年後見制度を利用するべきか?
家庭裁判所への申し込みは、どのようにすればよいのか?
このような相談には、私自身が、この制度を利用して、高齢者のお手伝いをしていますので、きっと、お役にたてるアドバイスができると思います。
裁判もできる
 裁判の代理といえば、弁護士さんの仕事ですが、「ケンカしている金額が140万円以下」「簡易裁判所での裁判」の裁判は、司法書士も代理することができます。昔、利息が高すぎた時代に、お金を借りた人が、「高すぎて、法律違反だった分の、利息を返して。」と、請求する、「過払金返還請求」(かばらいきん へんかんせいきゅう)」のことを、テレビのCMなどで見た・聞いた方も多いと思います。
裁判の代理といえば、弁護士さんの仕事ですが、「ケンカしている金額が140万円以下」「簡易裁判所での裁判」の裁判は、司法書士も代理することができます。昔、利息が高すぎた時代に、お金を借りた人が、「高すぎて、法律違反だった分の、利息を返して。」と、請求する、「過払金返還請求」(かばらいきん へんかんせいきゅう)」のことを、テレビのCMなどで見た・聞いた方も多いと思います。
これも、「お金を争う」ということですので、司法書士が、この仕事を行うこともあります。
しかし、私の事務所は、裁判の仕事を専門にしていません。相談はお聞きしますが、他の弁護士・司法書士を、紹介するかもしれません。

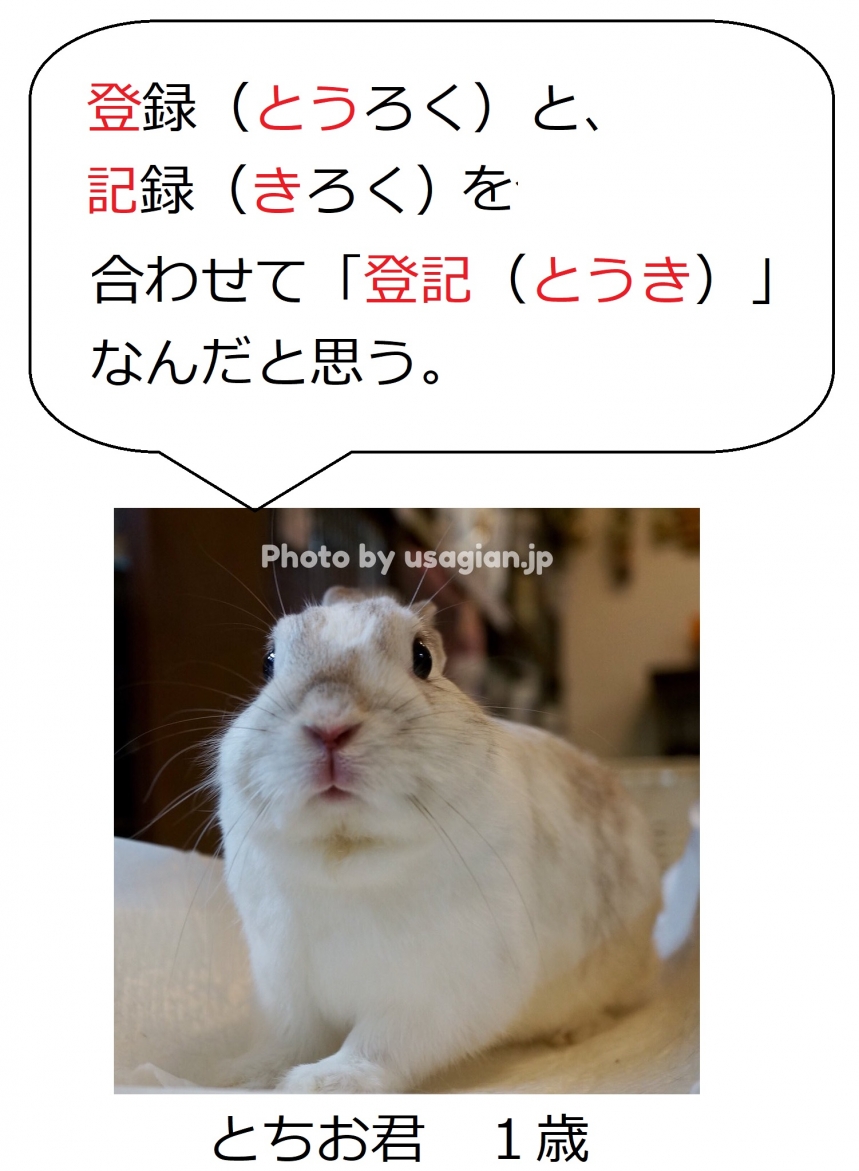 この土地・建物は、だれのもの?
この土地・建物は、だれのもの?









